No58メルマガ/4.ARROWS🏹2025年2月号
最近もロシア人やインド人、フィリピン人の方々から専門職の問合せや特定技能2号の就労の相談をよく受けます。今、日本にいる在留資格のある人たちにもかかわらず、新たな制度や手続き認識が日本社会も会社意識も低かったり、非協力的なところもあって彼らはとても優秀なのに関わらず、次の手続きが進められないでととても困っている人が多くいます。
今の在留資格が終わったら日本で引き続き長期で働きたい人にもかかわらず、諸条件もあり制度上では跳ねられてしまう場合もあり、とても不運で可哀そうです。一律の制度を設けて進める場合もあるでしょうが、なぜか特定の国を優遇する政策もあったり、もう一方では規定ルールのみで不許可にしたり、個人的には不平等な制度や政策はすぐにでも止めるべきだと思います。

特定技能の審査体制を入管庁が拡充!
今春に申請殺到予想
出入国在留管理庁は外国人材の在留資格「特定技能」の審査体制を拡充する。技能実習生として入国した人が特定技能に移る動きが春以降に加速することが予想される。審査が長引くと企業の人材確保に支障が出るため、担当者を増やして円滑な移行に努める。
入管庁は2025年度に定員増となる153人のうち半数以上の79人を特定技能などの担当に振り向ける。(日本経済新聞より)

外国人在留手続き手数料値上げ!
政府は1月31日、外国人の在留手続きの手数料を2025年4月1日から引き上げる政令を閣議決定した。在留資格の変更許可など8種の申請で400円〜2000円程度値上げする。出入国在留管理庁によると物価や人件費の上昇を考慮したという。
在留資格の変更と在留期間の更新は現行の4000円から6000円に引き上げる。永住許可申請の手数料は8000円から10000円に変わる。資格の変更許可や永住許可といった手続きについては1981年以来で戦後2度目の手数料改定となる。
オンラインでの申請は400〜500円低く設定する。鈴木馨祐法相は閣議後の記者会見で「入管手続きの円滑化や効率化を図るため、更なるオンライン申請の促進につながることを期待する」と説明した。
日本に来た外国人は旅行など短期滞在を除き在留資格の手続きをして入国する。この際に手数料はかからないものの、その後に資格を変更したり在留期間が満了して更新したりする場合には必要になる。地方入管の窓口で申請する。(日本経済新聞より)

事務職を求める日本人、安定した仕事を求める外国人
厚生労働省の「職業安定業務統計」では、2023年の平均有効求人倍率は1.31倍で人手不足しています。ただ、事務職の有効求人倍率は0.45倍です。これは、求職者100人に対して45件の就職先しかないという求職者にとって事務職に関しては、半分以上が事務職に就労できないという事になります。また、事務職では昇給を希望したり、キャリア形成を作っていくのはかなり厳しいのも現実です。
厳しい採用選考を通過して就職した会社で事務職でも、訳や理由があって辞めてしまった場合、再度、人余り市場でも転職活動をすることになるので、かなり難航する就職活動が待っています。条件の良い会社によっては、数十倍以上の倍率、応募者が殺到します。労働条件も事務職は決していいものではない。昨今、現場労働者の人手不足が深刻しており、ほとんどの職種で時給UPがなされているが、事務職は地方では特に横ばいで賃上げは期待できません。企業側も人余り状態の事務職はあまり苦労しなくても採用が出来ていますので、時給はここ数十年横ばいに近い状態です。
日本国内であれば物流、卸売り、小売り、製造業の現場では慢性的な人手不足が起きています。その現場を支えてきているのが、外国人の人たちです。よく日本人の仕事を外国人が奪っているという話を聞きますが、日本人には、人気のないあくまでも人が集まりづらい職種業種で特に外国人増えているのであって、ましてや一番増加しているのは、経験やスキルが必要な高度な人材が日本国内では外国人が最も増加しているのです。つまり、日本人とは競合はしていない分野なのが、現実なんです。
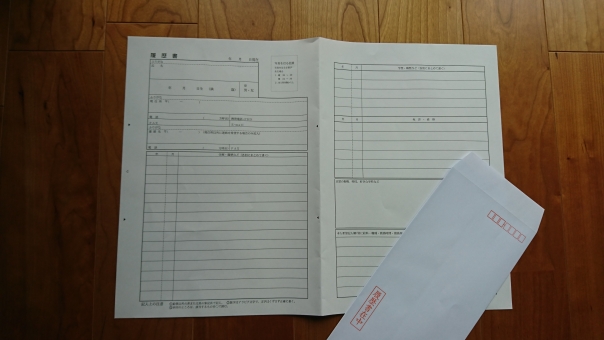
特定技能、外食業外国人の就労緩和でホテル宿泊業でもOK!
政府は、外国人労働者の中長期的な在留を認める「特定技能」制度に関し、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランで注文取り、配膳といった接客や調理に当たることを新たに認める方向で調整に入った。深刻化する人手不足が経営に悪影響を及ぼしている現状を踏まえた措置。お酌などの「接待」は引き続き不可とする。関係者が31日、明らかにした。(JIJI.COMより)
近く特定技能制度などに関する有識者会議に諮る。了承を得られれば、入管難民法に基づく分野別運用方針を今春にも改正する段取りを描く。特定技能は現在、一定の知識や経験が必要な1号として16分野、熟練した技能を要する2号として11分野が指定されており、「外食業」はどちらにも含まれる。ただ、外国人労働者の「安全な労働環境」を確保するため、風営法の許可を受けた飲食店では特定技能外国人の就労を一律に認めていない。

一方、旅館やホテルは芸者の舞踊などで客をもてなすため、風営法の許可を得ている事業所が多い。コロナウイルス禍後のインバウンド(訪日客)急増を受け、旅館やホテルのレストランでも人手不足が拡大。営業停止に追い込まれたり、宴会を中止したりするケースが相次いでいるという。
このため、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)などは規制の緩和を要望。政府は旅館・ホテルの食堂やレストランに限り、風営法の許可を受けていても就労を可能とする方向に傾いた。
対象とするのは特定技能1号と2号の両方。外食業で1号の業務内容は注文取りや配膳、調理と店舗管理とされ、2号はこれらと店舗経営となっている。風営法で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義される「接待」は禁じられている。

東京都内の外国人労働者数が約59万人で過去最高に
東京都内の国籍別では、中国が17万人超で最多、宿泊業・飲食サービス業が全体の2割を占める
東京都内の事業所で雇用されている外国人労働者数が約59万人となり過去最高を更新しました。 東京労働局によりますと、2024年10月末の時点で、東京都内の事業所で雇用されている外国人労働者数は58万5791人で前年から約4万3000人増え過去最高を更新しました。 国籍別では、ダブルカウントで1位、中国がもっとも多く約17万6071人、次いで2位、ベトナムの9万619人、それに3位、ネパール(5万1774人)、4位、フィリピン(4万304人)、5位、韓国(3万9914人)と続いています。 産業別では、宿泊業・飲食サービス業が最も多く、全体の2割にあたる約11万8000人で、次いで卸売業、小売業(9万8310人)となっています。

(FNNフジテレビ,社会部より)